タガヤっす。
ちょっと2日酔いかも知れません(汗)
先日、電脳卸の大将(木村くん)に電話したら留守電だったので、ドロップシッピングおつかれさまでしたと一言残しておいたら、昨日に折り返し電話があった。
近況報告をしてたら、呑みに行こうということになったので適当に誘ってみた。
ウェブシャークの大将
フェンリルの柏木くん
アーカムの畠中くん
オレ
途中で澤久も合流して、まったりと長時間呑んだ。
2次会は新地に繰り出し呑んだ。
1次会は大将のおごりで、
2次会はなぜか畠中くんのおごり。
ごちそーさまでした<(_ _)>
しっかし楽しいメンバーだった。
不満点は、畠中くんがどっかから借りて来た猫みたいな、いつもの切れ味がなかったこと。2軒目でおねーちゃん相手に切れ味を発揮しても意味ないからw
2軒目のお会計、知らんけど、怖いから知らないままでいよーっと(・∀・)
タガヤっす。
ウチで壮大なビジネスプランがあるという話を
このブログでも何度かやってきました。
お酒の場で、口の堅そうな友人には話していたプランなのですが、やっとこさサービスとしてリリースした会社が出ました。
http://www.conyac.cc/
完成度はまだまだ低いですが、
これから進化していくと思います。
このプランだけは、ウチもやらないという選択肢がないので、次に続きます!! 事業計画だけは1年以上も前から練りに練っています。
この競合の参加の意味はでかいです。
・市場を刺激する
・コンペティティブな環境でプランがブラッシュアップする
・認知度が勝手に上がる
・オレの尻に火がつく
うん、意味がでかいw
ってことで、そろそろ本気を出したいと思います(・∀・)
先日、友人とぶらぶら遊んでいるときに、運が良いって何?という話をしました。
運が良いというのは、宝くじが当たるだとかそのような話ではなく、最終的にはなぜか上手く物事が運んでる率、という感じの話だったのですが、友人も私も奇妙なほど仕事運が良いので、その原因を知りたいと思ったのです。
最初は、色々な話を見つけてくるタイミング、捨てるタイミングがベストだから上手くいっているのかなという話をしていましたが、
結局、「短期的に見て有利な選択」と「長期的に見て有利な選択」のどちらかを選ばなければいけない際に、「長期的」の方を選ぶ可能性が比較的高いために、タイミングが良いと言うよりも、どのようなタイミングであってもプラスの部分が蓄積されていくために最終的には上手くいき、運がよいように感じるのかなと。そのような結論になりました。
本当でしょうか。その時はそれで納得したのですが、書いていて色々と疑問が湧いてきます笑
タガヤっす。
あれ?
今気がついたが、HPで表示されへんようになってる(汗)
当社の立ち上げ時から協力してもらってる、
当社の顧問である早くんが出資してる会社が
いい感じらしい。
その名も「美人時計」。
アンテナが高い人は既に知ってると思うが、
知らない人のために。
http://www.bijint.com/jp/
キレイなおねいちゃんが、分刻みで登場して時間を教えてくれるのだ。iPhoneのアプリも出てるらしいが、WEBでも見れる。
◆
早くんは主に東京で活動してる人なのだが、
大阪出身でボクとの付き合いもそこそこ長い。
先日のWEB2.0イベントの打ち上げ会場にもなってたらしい。
Zeus地引さんからお電話でお誘いしてもらったのだが、
生憎ボクは大阪なので出席できず残念な思いをした(涙)
早くんからブログに書いてくれと言われて書いてみた。
最近、そんな注文が多いなー。
ボクのブログアクセス、1日のユニークで100ちょっとしかないよ?
ということは、月間3,000か。
少なっ!(涙)
でも、コンバージョンはいいと思うぞ(・∀・)
◆
コアでマニアックでカルトな読者のみなさま、
いつも愛読ありがとーございます!<(_ _)>
タガヤっす。
ボクはアイディアを出す、つまり「妄想」がとっても大好きです。
常に妄想してます。
ボクが今まで妄想した数々のビジネスモデルの中で、
現在、サービスになっているモノがたくさんあります。
やっときゃ良かった、とは誰もが考えることやと思いますが、ボクはそう思っていません。なぜなら、そこそこ利益を出してる会社さんはありますが、大儲けしてるとこがないんです。
やらなくて良かった。
心からそう思うんです。
その根っこには何があるのか?を書きます。
◆
妄想を実現するために必要なことは、
「金」「モノ」「情熱」やとボクは思ってます。
若い頃は全て持ってた。
だから無茶なことで儲けもしました。
その経験があるから、大抵のアイディアをボツにします。
規模感が大きくないとスタートしないんです。
年間で100億を超える売上る可能性があり、
利益率が90%を超える可能性があるモデルかどうか。
つまり、世界的に受け入れられるサービスで、
運営に掛かる費用が少ないかどうか。
それ以下は、バイアウト目的かプロモーションやと思ってます。ウチのサービスのひとつである「ValiSAFE」は、明確に「プロモーション」なのです。別に儲からなくてもいいんです。ウチはこんなこともできるんだよ、ということを知ってもらうためのサービスなのです。
ボクらはこれからもプロモーション用のサービスを複数リリースする予定でいます。サービス自体で儲かる必要はないんです。
じゃあ、どこで儲けるのか?
ここがキモですが、詳細は書けません(汗)
これでは尻切れみたいなエントリなので、ちょっと補足します。
◆
ここがタイトルの「継続する」に繋がります。
プロモーション用サービスで儲からなくてもいいと書きました。
でも、継続することでノウハウが蓄積できます。
このノウハウで、さらにプロモーション用サービスをリリースするか、既存サービスを拡充することができます。プロモーションだけでなく、ノウハウ蓄積が目的になりますと、継続するために必要なことはなにか?ということを突き詰めることになります。
・ランニングコストを徹底的に下げる。
儲けるためのサービスではないので大胆にいけますw
そして継続することで得られるメリットがコストを超えて大きくなります。これが将来的な粗利率90%に繋がるとボクは信じています。
◆
ひとつのモデルで失敗 = 終了
この方程式に当てはまらないようにしたい。
だから考え出した方法がひとつのモデルで大成功しない。でした。
でも、事業の多角化を目指しているわけでもないんです。
人々を幸せにするWEBサービスの企画、運営をしたい。
でもターゲットになる人々が「幸せ」と感じるポイントが違う。
だから、複数のWEBサービスをリリースするんです。
だから、多少失敗してもダイジョブなようにしていたい。
これがボクの経営哲学になってます。
Yahoo!が無料のアクセス解析ツールを提供開始したので使ってみました。
まず思ったのが
Analyticsに似ている・・・
Analyticsでできることはだいたいできるし、AnalyticsでできないことはYahoo!アクセス解析でもできないようです。(モバイルサイトの解析とか)
大きく違うのは操作性。
断然Yahooの方が使いにくい。
メニューをクリックしても下層のメニューが展開されるだけで、サマリーが表示されない。
直帰率を見るためには[ナビゲーション]-[直帰率]-[全訪問]-[URL別]と最後までメニューを展開しないと見ることができない。これはダメだろ常識的に考えて・・・
あとはいらんグラフを描写するのにいらんFlashが動きます。無駄だなぁ。
さらに言うと、字が小さい。
・・・なんかいじわるな姑みたいだけど、毎日見るものだからちょっとしたことが気になるんです。ごめんなさい。
で、落としてばっかりなのもアレなので1つだけいいところを。
Yahoo!アクセス解析は
超リアルタイムに解析できます。
Analyticsは解析結果が反映されるまで結構時間がかかるのですが、Yahoo!アクセス解析はリロードするたびにサクサク結果が反映されます。
知りたい時にすぐ見える。これはAnalyticsに対する最強のアドバンテージですね。
しばらく併用していくので、近日中に機能比較なんかもしてみようと思います。
前回の記事「オブジェクト指向型のプログラムの考え方(2)」
前回でクラスのfunction部分の作り方は何となくイメージしてもらえるようになったと思いますので、今回はクラスの変数やコンストラクタの使い方について書いていきます。
オブジェクト指向のプログラムを書く場合はこの変数の使い方にも注意しなくてはいけません。
クラスの変数に設定していいのは基本的に扱う対象のパラメータ関連のみと考えてください。
つまり、今回の場合では扱う対象がwordpress(以下WP)になるのでWP関連のパラメータや初期値で必要なものが対象になります。
今回はWPに接続するためにXMLRPCを使用しているのでWPに接続するためのオブジェクトが生成されます。この生成されたオブジェクトや、このオブジェクトを使用してWPにアクセスする場合にIDとPASSが必要になりますので、これらをクラスの変数として持ちます。
また、このように扱う対象に対して初期値が存在する場合は、それらをコンストラクタを使用して設定するようにします。
変数の悪い用法としてよく見かけるのですが、クラスの関数同士の値の受け渡しをしたいためにクラス変数を使用する人がいます。
前回書いたプログラムではsendXmlの時に$messageを変数として持たせておけば引数で渡さなくてもよくなるのでそのような使い方をする人もいますが、こういった使い方は極力やめて閉じた関数を書くようにしてください。
と、私はこんな感じでオブジェクト指向のプログラムを作成しています。
初めのうちは何となく形にはなっていても、他のシステムで再利用したりできるような物にはなっていないと思います。(私も手探りで作った部分や急いでいるときはこうなります。)
それでも多少読みやすく保守性もあがっているはずですし、そのソースを他のシステムで利用しようと改良したりしていくうちに綺麗な形になっていくと思います。
今回の例で「PHPからWPを操作する」をクラス化したプログラムを作成しましたが、製作途中のものでもよければ要望があれば公開もしたいと思っているので興味のある人はコメントしてやってください。
タガヤっす。
10年もネットにまつわるいろいろな商売をしていると、そろそろ気付くことがあります。ネット上にある日本のマーケットは飽和しているのではないか?ということに。
新規参入するマーケットとしてインターネットは、様々なコストを圧縮し、かつ全国をターゲットにできるインフラを提供してくれました。ところが、昨今ではアクセスを獲得するためには、SEO/SEMをはじめ、PPC広告やニュースリリースなど、様々な手法でプロモーションしなければ、アクセスを獲得することが難しくなりました。
商品やWEBサイトが悪い、クオリティが低いのではなく、スパムや情報商材、その他の阻害要因となるWEBサイトが乱立し、ユーザーは目的とする商品やサービスを探し難くなったんだと、ボクは考えています。
◆
だからボクは、WEBを利用する目的の転換が必要だと考えています。
EC1.0の目的が、
・マーケットの拡大
・コストの圧縮
だったとすると、
EC2.0の目的は、
・海外進出
・日本運営でコスト圧縮
なのではないか?と。
◆
そのために必要なこと。
1)ターゲットとする国の言語でWEBサイトを作成
2)海外での決済に対応
3)外国語でのやり取り(サポートなど)
一番敷居の高いのはやはり3番でしょう。
しかし、果たして本当に難しいことなのでしょうか?
やってみもしないで、「できない」って決めていいのでしょうか? 今を生きる経営者として、そんな安易な決断をしてもいいんでしょうか?
ボクはそんなに難しいことではないと思います。
例を挙げましょう。
・質問の内容は、ほとんどパターンが決まっている。
→ 日本語の質問でも一緒でしょ?
価格、納期、在庫、配送に関わる質問がほとんどです。
メール対応だけに限定すれば、翻訳サイトでこなせます。
・相手は問い合わせ先が日本であることを知っている。
→ 海外旅行などで、つたない日本語でもうれしいでしょ?
相手は完璧なやり取りを求めていません。
求めているのは、アナタの商品です。
むしろ、日本文化は海外では高評価です。
・やり取りに必要なのは、言語力ではなく誠意です。
→ 日本のお客さんの方が大変なように思いますw
◆
参入障壁を低くし、リスクを最大限に排除することができれば、比較的簡単にグローバル企業の仲間入りができると思います。
◆
先日、ふらっとウチに遊びに来た知人と情報交換している中で、東大阪のメーカーさんが販路拡大したいと言っていた、という話を聞き、「そんなん海外に売ったらええがなw」って気軽にアドバイスしたんですが、彼らの想像上で「海外を相手にする」ということを、実物以上の障壁を感じていることがわかったんです。
#海外には絶対にないクオリティの高い商品ですw
#しかも、絶対に売れることを命掛けてもいいぐらいわかってる。
そこ、商売になるがな(・∀・)
と思って、こんなエントリを書いてるオレは、絶対に商売がへたくそだと思う訳です。
#リスクヘッジの内容を書かなかったオレ、エラいw
英語が話せるだけ(読めない)ですけど、絶対に海外に支社出したるねん!!
最近meta http-equiv=”refresh”が機能せずに真っ白なページが表示されるので
「今はやりのGENOウイルスにやられた!?」
と思ったらはてなブックマークFirefox拡張のせいらしい。
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/11285/
から1.1.4以降のバージョンをインストールすれば解決します。
まったく人騒がせな。
タガヤっす。
友人が面白いエントリをしてるのでフォローしてみる。
◆
アーカムでできること。
http://arcam.typepad.jp/arcamstaff/2009/05/post-febc.html
ふと疑問が。
著作権者に中古書籍販売利益を還元すると紙媒体を守れるのか?
ボクは単純に、
そんなことをせんでも紙媒体は無くならないと思う。
ボクの持論を展開する前に、一応印税についておさらいしておく。
書籍に関する収入って、属に「印税」って言われてる。
印刷部数もしくは実売部数に応じて、出版社が著作者に支払う
ロイヤリティのことを言うのだが、つまりは出版社と著作者の契約なのだ。
最近テレビでも問題になってるのは、中古書籍よりも
マンガ喫茶の乱立に注目される傾向にあるようだ。
購入せんでもマンガ喫茶に行ったら目的のマンガがある。
新品を購入すらしないで済むのが問題なのだ。
昔、カラオケで同じような問題になったことがあった。
カラオケで著作料を支払わないお店が多発したと記憶してる。
音楽のような著作権管理団体がマンガ喫茶に行き、
著作料を徴収する必要があるのではないかとボクは思うんだ。
同じ著作物であるのに、音楽と書籍じゃあ管理の仕方が大分と
違うように見える。ってか事実そうなのだろう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E7%A8%8E
音楽には著作権協会があるが書籍にはない。
書籍の著作権協会を作って健全な市場を維持する方向に向かえばいいのに。
友人の何人かに漫画家がいるが、とても過酷な職業のようだ。
このような取り組み自体には賛成なのだが、
中古書籍の販売収入から支払わなくてもいいような気はする。
でも、貰えるもんはもらっとけといいたい(・∀・)








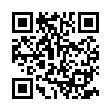
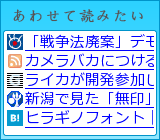



最近のコメント