突然ですが昨日ファミスタやったんです。ハンゲームの方じゃなくて、リアルなファミコン版のファミスタ’91を。
’91というだけあってグラフィックは古臭くて、サウンドはチープで、戦術なんてあったもんじゃない。でもね、すごく面白いんです。十数年前のゲームなのに。
なぜか?
その理由の1つに「シンプルさ」というのがあると思うんです。
なにしろファミコンなので、十字キーとAボタン、Bボタンしかありません。操作に迷いようがないんです。そして出来ることも少ない。だからプレイしてすぐに対戦者との駆け引きに集中できました。
と同時に「これってWEBサービスでも同様なのでは?」と思いました。
シンプルで迷わないインターフェース、シンプルで迷わない機能がサービス利用への障壁を下げ、結果的に多くの人に役に立つサービスを生み出すのではないかということです。
僕らのミッションは、より多くのユーザーに喜んでいただけるサービスを提供すること。
であれば、いかにカンタンでシンプルなサービスを作り出し、気負いなく使ってもらうか、これが初期フェーズでは特に重要なはず。
すぐに欲張ってしまう僕は気をつけなくては、と再認識しました。
さて、昨日あたりからIE7の自動更新がはじまって、一般人のメインブラウザはIE7になってしまったと思います。
対する僕は、メインでFirefoxを使っているのでIEのバージョンなんてどちらでもいい派です。ちなみに、自動更新をOFFにしてIE7は入れてません。
ただ、WEBサイトの動作確認のためにしばらくはIE6、IE7両方を使う必要があります。
ここで問題なのは、通常の手順でIE7を導入するとIE6が使えなくなるという点です。要するに二者択一なんですね。
そこで、IE7スタンドアロン版を導入してみました。
Internet Explorer 7 running side by side with IE6. (standalone)
http://tredosoft.com/IE7_standalone
上記サイトの「Download Internet Explorer 7 standalone Installer (427KB)」からインストーラをダウンロードしてインストールするだけです。カンタンです。
マイクロソフトの正規版ではないので、動作保証はされてませんが、サイトの動作確認には十分では。
1台のPCでIE6とIE7を共存させて併用したい「どちらも使いたい派」の方はどうぞ。
ヨドバシ、ヤマダ、ビックカメラなどの家電量販店に行くと、入り口付近にはだいたいデジカメ売り場があります。
それほどデジカメが売れ筋商品ということで、実際にいつも人だかりができています。
この光景を見ると毎回思うのが、「これだけデジカメが売れているということはたくさん写真が撮られているはずだが、みんなは撮った写真をどうしているんだろうか?」ということです。
ファイルム時代はほぼ撮影→現像ONLYだったわけですが、現在はデジカメで撮影した後に
- メディアをお店に持っていってプリント
- PictBridge対応プリンタでプリント
- パソコンに取り込んで写真共有サービスにアップ ex)livedoor PICS、フォト蔵、Flickrなど
- パソコンに取り込んで家のプリンタでプリント
- パソコンに取り込んでオンラインプリントサービスでプリント
- 家のパソコンに取り込むだけ
僕の場合は、だいたいパソコンに取り込んでオンラインプリントサービスでプリントします。
それはなぜか。
「写真が趣味で、美しく耐久性のある写真にしたい」
「ITに詳しいのでパソコンに取り込んで編集するのが苦ではない」
「オンラインプリントサービスが一番安あがり」
という理由からです。
しかし、オピネットが行った「写真プリント方法についてのアンケート」によると、48.1%の人が家でプリント、26.8%の人が店頭で注文、11.9%の人がネットで注文、そして25.3%の人がプリントしないそうです(複数回答)。
ヒジョーに残念です。
家でプリントすると、プリンタによっては対光性・対ガス性があまりよくない写真になってしまいます。
店頭で注文するのは面倒で、しかも1枚30円~35円と割高です。
プリントせずにWEBにアップするのもいいですが、わざわざケータイではなくデジカメで撮った写真なんだからプリントして見るほうが満足度が高いと思います。
たぶん一般の人たちにはパソコンに取り込んで色々やるのが面倒orよくわからないんでしょうね・・・。
僕はこの状況をなんとかしたい。今はなんとかできる状態ではないですが、そのうち、しかし絶対になんとかしたい。
みんなが写真をカンタンに、そして安くプリントして楽しめるようなサービスを提供したいと(勝手に)思ってます。
ケータイメールを見直した
この前、ヤフオクでプレイステーションを売ろうと物置を漁っていたら、「かまいたちの夜」が出てきました。「かまいたちの夜」はサウンドノベルの代表作で、僕にとってすごく思い入れのあるゲームです。
せっかくなので売る前に一度プレイしておこうかな、と思いました。と同時に、腰すえてやるのメンドクサイ、とも思いました。
もう僕の体は、据え置き型ゲーム機に耐えられる体ではなかったんです(笑)
そこで、DSかケータイでリメイク版がないか探してみると、あのニコニコ動画のニワンゴから「かまいたちの夜 ニワンゴ版」がリリースされていました。
http://niwango.jp/pc/kamaitachi/niwango_kamaitachi.php
しかし、アプリではなくメールでプレイするとのこと。
???でしたが、とりあえずニワンゴに「かまいたち」とメールを送ってみました。
すると、僕の携帯電話にニワンゴからメールが届き、そこには「かまいたちの夜」のプレイ方法、ストーリーが書かれていました。
要するに、選択肢を送信するとストーリーが返ってくるサウンドノベルだったのです。
衝撃でした。
これなら操作は超カンタン、しかも歩きながらでもプレイできる、セーブの必要なし、まさに「誰もが、いつでも、どこでも」のユビキタス(死語)じゃないですか。
しかも、メールを利用するということは、広告の開封率が・・・なんて思うじゃないですか。(あさましい?)
ケータイメールなんて単なるコミュニケーションツールの1つとしてしか考えていませんでしたが、見直しました。
まぁ一番衝撃だったのは、そんなことに今更気づいた僕の頭脳だったわけですけれども(涙)
PCからGoogleモバイルにアクセスする
今日の今日まで知らなかったんですが、http://www.google.co.jp/m/search
でPCからGoogleモバイルにアクセスできるようです。
これで、携帯サイトの検索結果をPCでサクサク調べることができます。
他にも、
<form action="http://www.google.co.jp/m/search">のようなコードで検索することによって、Googleマップにもアクセスできます。
<input name="q" size="20"><input type="submit" value="検索">
<input type="hidden" name="hl" value="ja">
<input type="hidden" name="output" value="chtml">
<input type="hidden" name="ie" value="Shift_JIS">
<input type="hidden" name="oe" value="Shift_JIS">
<input type="hidden" name="site" value="maps">
</form>
どうしてこんな事をやっているかというと、コーポレートサイトに地図を表示してなくて、お客様が迷われたようなんです。
ヒジョーに恥ずかしい限りです。
そこで、Googleマップで地図を表示すると同時に、QRコードでモバイル用の地図へのリンクを貼ってみました。
こんな感じです。
ちょっとは便利になったのではないでしょうか。
今までムリだと思っていましたが、ログインが必要なサイトでもAdsenseが貼れるようです。
ログインを要求するページに対して、クローラのアクセスを許可する方法を教えてください。
AdSense ヘルプ センターより
※場合によってはまずログイン情報を更新する必要があるようです。
ということは、自社サービスの管理画面にAdsenseを表示、なんてこともできるんでしょうか。
ユーザーの目的も属性も絞れているし、広告配信先としては最適なんじゃないかと。
サービスが立ち上がったら、さりげなく試してみたいと思います。
ただ、管理画面なのでマッチするコンテンツに難ありかも。
CTRがどうなるのか楽しみです。
少し前に、IDEA*IDEAで「Yahoo! Shortcuts」というWordPressプラグインが紹介されてました。
キーワードにマッチした写真や地図を自動で挿入してくれる、最高にCOOLなプラグインです。
ただ・・・
日本語に対応してないんですよね・・・。
ヒジョーに残念だったので、解決策を色々検索していたら「Gigazinize Tools – Image」という似たようなサービスを見つけました。
要するにエントリの最初に写真を入れて、GIGAZINEみたいにしよう!というツールです。写真はFlickrから引っ張ってくるみたいです。
やっぱりイメージ写真があると、ひと目でエントリの内容が推測でき、テキストを読んでもらいやすくなります。
これは導入すべきだな、というわけで、試しに社名の「ASENS」で検索してみました。

- Photographer
- gordontour
- License
- Creative Commons (by-nc-nd)
- Tool for photo selecting
- Gigazinize Tools – Image
ちなみにこの写真、「Monument of the Asens」というものらしいです。
そういう地名があるんでしょうかね。謎です。
アクセス解析ツール「なかのひと」を入れてみました
Google Analyticsは無料で、確かに便利なアクセス解析ツールです。ASENSでも導入しています。
でもちょっと物足りない・・・。
数字だけじゃなくてもっと直感的なデータが欲しいんだ!
というわけで、アクセス解析サービス「なかのひと」を設置しました。
「なかのひと」を利用すると、このブログにどんな組織の人がアクセスしてきたかがわかります。
解析結果に、企業とか大学とか公共機関の名前がガチで表示されるわけです。
今はアクセスが少なくて、何の役に立つんだろって感じですが、将来的に「なかのひと」きっかけでアライアンスなんかが発生すればいいなぁと思います。
アクセスしてきたユーザーの年代や性別を推測する機能もあるので、WEBサービスが立ち上がったら導入してみたいですね。
遅ればせながら、明けましておめでとうございます!
正月は、ひたすら姪とたわむれておりました。(いやぁ、こどもって癒されますね)
その他、いい機会なので自宅のPC回りの大掃除をしました。
まず、ダイナミックDNSで運営していた家サーバのコンテンツをhetemlに移動し、サーバを撤去しました。
次に、アクセスポイントとFONルータで二重化していた無線をFONに一本化しました。
アクセスポイントが余ったのでヤフオクで売ろうと思ったら、他にも色々使ってないデバイスがあるなぁと思い出し、物置きをガッツリ整理しました。
最後に、PCの中身を見直し、半年以上アクセスしていないようなゴミファイルをごっそり削除しました。
ここまでやると部屋だけでなく、気持ちまでスッキリします。
要するに管理するものがなくなった分、心理的ストレスが減るんですね。
思い切って捨てる⇒シンプルに生きる(仕事する)⇒新しい事にチャレンジする⇒以下ループ
今年はこういうことができる人間になりたいです。
というわけで、今年もよろしくお願いしますm(_ _)m
12月13日にMovable Type オープンソース・プロジェクトの開始が発表されました。
MTOS: Movable Type オープンソース・プロジェクト
http://www.movabletype.jp/opensource/
US公式サイトの情報によると、今のところ、Movable Type Open Source(以下MTOS)と商用のMovable Type4に機能的な違いはないようです。
http://www.movabletype.org/2007/12/movable_type_open_source.html
「MTOS has every feature in Movable Type 4.0」
こうなると、最近WordPressに浮気気味の僕も、Movable Typeへの元サヤを検討してしまいます。
というわけで、MTOSとWordPressを勝手な視点で比較してみました。
使用したMTOSはバージョン4.1、12/14版のnightly build、WordPressはWordPress ME2.2.3です。
| MTOS | WordPress | |
|---|---|---|
| ライセンス | GPL | GPL |
| ページ生成方法 | 静的or動的(ダイナミックパブリッシング) | 動的 |
| カテゴリ | サブカテゴリまで対応 順序の指定は不可 |
サブカテゴリまで対応 順序の指定は不可 |
| テーマ | フリーではあまり多くない | 世界中にわんさか |
| エディタ | WYSIWYG | WYSIWYG |
| ファイル管理 | Ver.4から対応 | あり |
| カスタムフィールド | Ver.4.1から対応 | 対応 |
| ページ機能 | Ver.4から対応 | 対応 |
| 複数ブログ | 対応 | 対応していない |
| プラグイン | 多いが、ダイナミックパブリッシングに すると動かないものがある |
多い |
| 日本語ドキュメント | 多い、six apartの公式情報あり | 多い? |
| サポート | 有償でsix apartのサポートが受けられる | ユーザーフォーラム等で対応 |
つまり、機能の多さよりも、確実に動作することが求められるような企業サイト制作にはMovable Typeを、読ませるためのデザインや仕掛けが必要なブログ制作にはWordPressを、というように用途によって使い分けるのがベストだと思います。








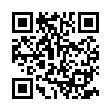
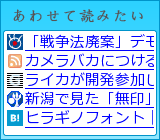



最近のコメント